「子どもが欲しいから食生活にも気をつけて、何度も排卵検査薬を使ってきた。でも、毎月やっぱり月経がきてしまう。周りの友達は次々に子どもが産まれていくのに。」
こんな状況に置かれると「もしかして自分は不妊症なのかな?」と胸が押しつぶされそうになります。
「病院に行ったほうが良いのかな?」
「不妊治療はいったいどんなことをするの?」
妊娠に悩む女性が病院に行くとき、不安が大きく勇気がいるのが事実です。
本記事では、最初に病院へ行くタイミングや治療方法など、不妊治療の全体像を紹介しています。
不妊治療はどんなことをするのかということが分かれば、不安感もやわらぐものです。ぜひ最後まで読んでみてください。
この記事でわかること
- 不妊症の特徴と原因
- 不妊治療とは
- 病院へ行くタイミング
- 不妊症の検査内容
- 不妊治療の種類と方法
不妊症とは
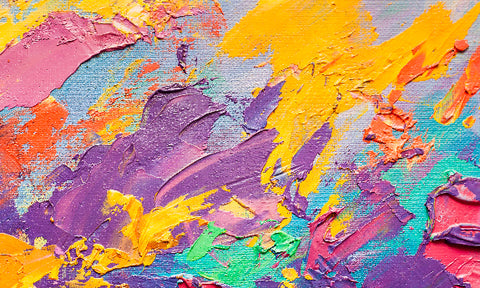
不妊症とは「妊娠を望んでいる健康な男女が避妊をせずに性交しているにも関わらず、一定期間妊娠しないこと」と日本産婦人科学会で定義されています。一定期間とはどのくらいの期間かというと、一般的には1年です。
不妊に悩むカップルは10組中1組の割合と言われていますが、実際にはもっと高くなるという見解もあります。なぜなら近年は晩婚化で妊娠を考える年齢自体が高くなっているからです。
厚生労働省の人口動態統計によると、婚姻件数は1972年の約100万組をピークに年々減少し、2017年では過去最低の約60万組に減少しています。
同時に第一子出産時の母親の平均年齢も上昇。1985年は26.7歳だったのに対し、2017年は30.7歳と4歳も上昇しているそうです。
不妊の原因
女性側の不妊症の原因は、主に5つに分けられます。
- 排卵因子:排卵が起こらない排卵障害による不妊
- 卵管因子:卵管の詰まりや卵管周囲の癒着による不妊
- 子宮因子:子宮筋腫・子宮内膜ポリープなどによる不妊
- 頸管因子:子宮頸部の手術や炎症などによって起こる頸管内(子宮の入口部分)の粘液異常による不妊
- 免疫因子:免疫異常によって体内に精子を攻撃する抗体ができたことによる不妊
しかし、不妊症の10~15%は原因が分からないと言われています。近年、不妊に悩む高年齢の女性が増えていることもあり、原因不明の不妊症が増えつつあります。
不妊治療とは
不妊治療とは、不妊の原因を調べて、それぞれの原因にあった治療を行うことです。不妊治療は大きく一般不妊治療と高度生殖補助医療に分けられ、治療をしても妊娠しない場合は、さらに効果が期待できる治療へとステップアップします。
2022年4月から不妊治療でも保険が適用されるようになり、不妊の検査や治療における経済的な負担が軽くなりました。しかし、年齢や回数など制限があるため、不妊に悩む方は、早めに相談することをおすすめします。
不妊治療で病院に行くタイミングは?

「もしかしたら不妊なのかも?」と感じ始めたときが、不妊治療で病院に行くタイミングです。
不妊治療を始めてもなかなか妊娠できず、長い年月がかかるケースがあります。1年妊活をしても妊娠しない場合は不妊治療が勧められますが、年齢によっては早く不妊治療を始めないと、妊娠できる確率が下がってしまう可能性があるので、できるだけ早めに医師に相談しましょう。
もし、婦人科系の病気が不妊の原因となっている場合は、早期の治療が必要です。少しでも不妊に対して不安がある場合は、早めに医師に相談し、それぞれにあった治療を始めることをおすすめします。
不妊症の主な検査内容

不妊症で治療が必要かどうかを診断する6つの検査内容を紹介します。
不妊症を乗り越えて妊娠にたどり着くには不妊症の原因を明らかにすることが重要です。不妊症の原因が判明して初めて、効果的な治療を選択することができます。
全ての検査に大切な意味があるため検査のやり方だけでなく「この検査で何がわかるのか?」を理解して検査に望んでください。
基礎体温の測定
心身ともに安静な状態の体温のことを基礎体温といい、目を覚ましてから起き上がる前に横になったまま測定します。
基礎体温の測定には婦人体温計という、一般的な体温計より細かく数値が表示される専用の体温計を使用し、舌の下に体温計をはさんで毎日測定・記録します。
2~3周期にわたり基礎体温をグラフとして記録することで
- 排卵が正常に起こっているか?
- 排卵日はいつか?
- 黄体ホルモンが分泌されているか?
などの参考にすることができます。
内診・経腟超音波検査
内診は婦人科診察室の診察台の上で行われる検査です。子宮や卵巣に腫れがないかや、押したときに痛むところがないかを医師が実際に触って確認します。
経腟超音波検査も診察台の上で行われる検査で、直径1.5~2cm程度の超音波プローブを腟に挿入します。
経腟超音波検査はリアルタイムで体内の様子が画像として表示されるため、子宮や卵巣に異常がないかが診断できます。卵胞の大きさも確認することができ、ほぼ正確に排卵日の予測が可能なのも特徴です。
血液検査
一般的な採血と同じように血液を採取し、女性ホルモンや男性ホルモン、卵胞を刺激するホルモンなど、各種ホルモンが正常に分泌されているかを検査します。ホルモンの分泌量を調べることで、子宮や卵巣が正しく機能して排卵などが正常に行われているかを判断します。
ホルモン検査のほかに糖尿病など全身の疾患がないかも同時に検査するのが一般的です。排卵前後で体内のホルモン量は変動するため、月経期(排卵前の時期)と黄体期(排卵後の時期)などにわけて検査を行います。
子宮卵管造影検査
月経終了後から排卵日までのあいだに行う検査で、子宮内に造影剤を注入します。レントゲンで使われるX線を使って、精子の通り道である卵管が癒着して詰まっていないかや子宮の形・卵管の形や太さなどを調べることができます。
約1mmという細さの卵管にネバネバとした造影剤を注入するため、個人差はありますが多少の痛みをともなう検査です。
しかし子宮卵管造影検査を行ったあとに自然に妊娠する可能性もあります。
フーナーテスト
フ―ナーテストは精子頸管粘液適合検査とも呼ばれ、子宮の入口である女性の頸管から出る粘液と男性の精子にどのくらい適合性があるかを調べます。
検査は排卵期に行われ、通常の性交を行った翌日に病院で子宮頸部から粘液を採取。女性の子宮頸管の中でどれくらい泳いでいる精子が存在するか?精子はどのくらい前進する力があるか?ということがわかります。
フ―ナーテストは男女ともに問題がない場合でも悪い結果が出ることがあるため、結果が不良の場合は翌月の排卵期に再検査を行うことがあります。
精液検査
精液検査は男性側の不妊要因を判断する検査です。WHOによって規定された正常基準値に照らし合わせ、以下のような項目を検査します。
- 精液量
- 総精子数
- 精子濃度
- 前進運動率
- 総運動率
精液を提出する必要があり、2-7日間程度の禁欲期間(射精をしない期間)のあと用手法(マスターベーション法)で精液を採取します。
精液の性状は温度に敏感なので病院で採取するのが理想です。しかし20℃から30℃以下に保ち、採取してから2時間以内に持参して検査することができる病院もあります。
不妊治療の流れ
不妊治療の流れを紹介します。
- 初診
- 不妊検査
- 一般不妊治療
- 高度生殖補助医療
不妊治療は、まず初診で過去の治療歴や方向性の確認、治療内容の相談を行います。不妊や治療に関して不安がある場合は、気軽に医師に相談しましょう。治療内容を決めるためには、不妊検査が重要です。超音波検査やホルモン検査、子宮卵管造影検査などで不妊の原因を確認します。
不妊治療は、一般的に段階的に行われることが多いです。まずは一般不妊治療(タイミング療法、人工授精など)を行い、それでも妊娠できない場合は、高度生殖補助医療(体外受精、顕微授精)へと進みます。
不妊治療の種類は?どんな方法がある?

不妊治療の種類は、以下のやり方があります。
- タイミング法:排卵に合わせて性交渉を行い妊娠確率を上げる方法
- 排卵誘発法:内服薬や注射薬で排卵を誘発する方法
- 内視鏡手術:子宮筋腫・子宮内のポリープの切除、卵管の詰まりを無くす手術を行い不妊の原因を取り除く方法
- 人工授精:排卵に合わせて人工的に精子を子宮内に注入する方法
- 体外受精:卵子と精子を混ぜ合わせることで受精させ、受精卵を子宮に戻す方法
- 顕微授精:1つの精子を卵子へ直接注入し、受精卵を子宮に戻す方法
以下の記事も合わせて読む
不妊治療の第一段階、タイミング法ってどんな治療法?費用や妊娠確率は?
まとめ
不妊症の原因は様々です。カップルのどちらかにはっきり原因がある場合もあれば、特に原因はないけれど妊娠しにくいというケースもあります。
「なかなか授からない」と悩み続ける前に、病院を受診して不妊の原因を検査してみることをおすすめします。特にカップルどちらかの年齢が高かったり、2人とも年齢が高い場合に妊娠を望むときは早めの受診が必要です。
不妊症の治療には様々な種類がありますが、自然妊娠に近い形で治療できる方法も多くあります。まずは不妊の原因を判明させ、心と体のバランスを取りながら治療を進めていくことが肝心です。
パートナーやかかりつけの医師と相談しながら、無理のないペースで妊娠を目指してください。








